委員会活動Committee
看護研究の玉手箱(過去)
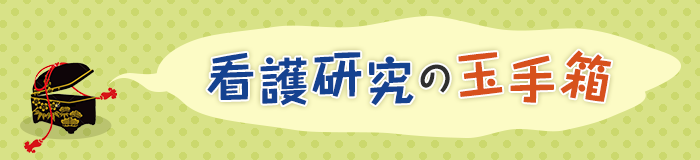
2022年度
妊娠中のパートナーからの暴力と幼少期の不適切な被養育体験が及ぼす新生児への不適切養育への影響
キタ 幸子
抗がん剤の血管外漏出予防に向けた投与局所の不顕性炎症の実態調査
阿部 麻里
放課後等デイサービスで医療的ケア児を受け入れるための必要条件
大槻 奈緒子
乳児との対面接触による妊婦の対児感情と不安への効果:ランダム化比較試験
園田 希
2021年度
⾼齢者の便秘アセスメントのために直腸エコー画像から便貯留・硬便貯留を検出するAIの開発
松本 勝
内視鏡を⽤いた嚥下観察の看護師向け教育プログラムの安全性と有効性
吉田 美香子
抗がん剤点滴の後の⽪膚が硬くなるのはどんな⼈?
阿部 麻里
2020年度
不妊治療中の男性のQOLには何が関連している?
朝澤 恭子
気管挿管患者の口腔ケア方法は拭き取る方がいい?、洗い流す方がいい?
村松 恵多
生体肝移植後の高齢レシピエントは、必要な自己管理行動を継続できているのか?
堀部 光宏
2019年度
精神疾患をもつ人へのアウトリーチ支援で、機能が良くなった人にはどのような支援が行われていたのか?
角田 秋
小児がんの子どもの気持ちを看護師はどうやって理解する?
秋田 由美
乳房の異常に気づきつつも医療機関の受診が遅れるのはなぜだろう?
大城 真理子
平成30年度
ひとは,からだをブランケットで覆われると,緊張がやわらぎ安心する
徳永 なみじ
介護が必要な高齢者の「飲み込む力」は生活の質を高める
森崎 直子
看護師が入院患者の転倒転落リスクを調べるためのアセスメント表の作成
東恩納 美樹
しつけと虐待の境界はどのようなものなのだろう
細坂 泰子
“しびれている身体”を知ることから始めよう!
坂井 志織
「妊婦が自らに合ったつわり軽減方法を見つけることを支える看護プログラム」の効果
岩國亜紀子
治療のためにマスクタイプの人工呼吸器を使用する患者さんが必要とする看護支援とは?
村田 洋章
筋肉のリラクセーション法の活用による認知症の人の心と行動の変化
池俣 志帆
平成29年度
からだを温めることで便秘症状と生活の質を改善する
吉良いずみ
電子カルテに看護師が入力する日々の患者データを使った、入院患者の日々変化する転倒リスクを、自動的に判別する人工知能の開発に関する研究
横田慎一郎
平成28年度
不妊治療中のカップルに対するパートナーシップ支援プログラムの必要性
精神的苦悩が少なく治療継続していただくために
精神的苦悩が少なく治療継続していただくために
朝澤恭子
「自宅の安全対策プログラム」は高齢者の転倒を予防する
亀井智子
背中のオイルマッサージには産後の女性をリラックスさせる効果があるのか?!
ケニヨン充子
東日本大震災後に仮設住宅団地の住民が必要としている社会的支援
寺本千恵
平成27年度
一人一人の朝を創るモーニングケアとは?
大橋久美子
筋肉内注射を安全に確実に実施するためには?
高橋有里
ドメスティック・バイオレンス(DV)被害を受けている女性は、どのような思いを抱きながら妊娠~産後を過ごしているのか?:DV被害からの回復プロセス
藤田景子
発達障害の子どもの‘人とかかわりたい’思いに応える看護
山内朋子
平成26年度
妊婦の冷え症はお産を長引かせる
中村幸代
筋委縮性側索硬化症(ALS)の人が、人工呼吸器をつけて生きるということ
平野優子
平成25年度
起きるケアで寝たきり予防!
大久保暢子
精神科訪問看護とはどのようなサービスか
角田秋
食事日記を活用したクローン病患者の食事支援プログラムの開発:食事“制限”から“拡大”へ
布谷麻耶
平成24年度
新生児集中治療室におけるファミリー・センタード・ケアにとって大切なこと :赤ちゃんと家族へのより良いケア実践を目指して!
浅井宏美
知的発達障害児の家族の力(ファミリーレジリエンス)を育むには?
入江安子
在宅モニタリングのテレナーシング(遠隔看護)で病状の悪化が抑えられる 慢性閉塞性肺疾患(COPD)で在宅酸素療法(HOT)を受ける方へ
亀井智子


